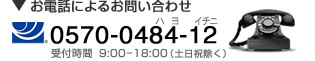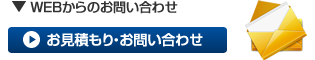人材派遣のコンプライアンス
人材派遣事業は、労働基準法や労働者派遣法などの法律が適用されます。
ワーカーズプロでは、"人材派遣のコンプライアンス"を経営の重要課題と位置付け、企業の皆様に安心してお取引いただけるよう法令および企業倫理を守り、
適正な事業活動を行うことが責務だと考えております。
そこで、企業様との相互理解を深めるため、ご理解いただきたく願います。
労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業とは、『派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、
この派遣先のために労働に従事させることを業として行うこと』をいいます。一般労働者派遣事業を行おうとする者は許可が必要で、ワーカーズプロ(株式会社シスプロ)も許可をうけています。
人材派遣という事業は、派遣先企業、派遣元企業、派遣スタッフの3者で成り立っています。
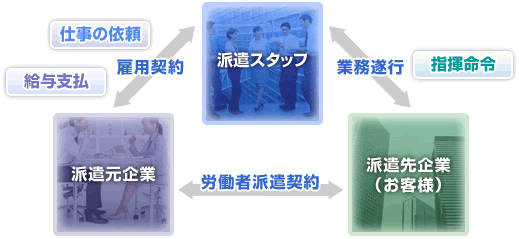
雇用関係と使用関係が分かれており、スタッフが実際に仕事をするのは派遣先です。
派遣労働は、労働基準法、労働安全衛生法などの適用を受けるのですか?
派遣元・派遣先は、労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法の適用を受けます。
具体的には派遣元が雇用主として労働契約、賃金、割増賃金、有給休暇、就業規則などの責任を負います。
派遣先は使用者として労働時間、休息、休日などについて責任を負います。
共通責任事項は均等待遇、強制労働の禁止、記録の義務、安全衛生の確保などがあげられます。
1年を超える派遣を受け入れようとする場合はどうなりますか?
派遣受入期間制限のある業務の場合、派遣受入ができる期間は、原則1年です。これを最長3年まで延ばすことができますが、 派遣先で雇用されている労働者の過半数を代表する者の意見を聞く必要があります。
労働者派遣契約の定めなければならない項目とは?
労働者派遣(個別)契約は、今後の全ての書類(就業条件明示書、派遣先管理台帳など)の基本となるものです。
派遣法では、派遣元と派遣スタッフを受け入れる派遣先との間で、最低13項目を定めなければならないとされています。
派遣先責任者を選任しなければなりませんか?
派遣先は派遣元との連絡調整や派遣就業の管理などを行うために、派遣先の雇用する労働者の中から、専属の派遣先責任者を選任してください。
派遣元との連絡調整の体制を確立し、苦情などの迅速・適切な対処などを行ってください。
派遣先管理台帳とは?
派遣労働者の適正な就業管理するためのものです。
派遣先が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに一定の必要事項を記載しなければなりません。
派遣先管理台帳に記載した事項の使い方は?
派遣元事業主に書面の交付などにより1ヵ月に1回以上、一定の期間を決め派遣労働者ごとの通知を行わなければなりません。
派遣先管理台帳の保存期間はどのくらいですか?
派遣就業の終了した日から3年間です。
派遣先管理台帳を電子情報として保管しても構いませんか?
必要なときに直ちに記載事項が明らかにすることができ、かつ写しを提供できるシステムとなっていればコンピュータで管理しても構いません。
派遣受入期間の制限のない業種はありますか?
以下のものがあります。
政令で定める業務として掲げる26業務(制限なし)
| 1号 | 情報システム開発 | 14号 | 建築物清掃 |
|---|---|---|---|
| 2号 | 機械設計 | 15号 | 建築設備運転等 |
| 3号 | 放送機器操作 | 16号 | 受付・案内、駐車場管理等 |
| 4号 | 放送番組等の制作 | 17号 | 研究開発 |
| 5号 | 機器操作 | 18号 | 事業の実施体制の企画・立案 |
| 6号 | 通訳・翻訳・速記 | 19号 | 書籍等の製作・編集 |
| 7号 | 秘書 | 20号 | 広告デザイン |
| 8号 | ファイリング | 21号 | インテリアコーディネータ |
| 9号 | 調査 | 22号 | アナウンサー |
| 10号 | 財務 | 23号 | OAインストラクション |
| 11号 | 取引文書作成 | 24号 | テレマーケティング営業 |
| 12号 | デモンストレーション | 25号 | セールスエンジニアの営業・金融商品の営業 |
| 13号 | 添乗 | 26号 | 放送番組等における大道具・小道具 |
■有期プロジェクト業務(制限なし:行政解釈で3年)
※事業の開始・転換・拡大・縮小又は廃止のための業務であって一定期間(3年)内に完了することが見込まれること
■日数限定業務(制限なし)
※その業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1ヵ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下の業務
■産前産後休業・育児休業など母性保護又は子の養育をする為に休業している人の代わりの業務(職場復帰するまで)
■介護休業など対象家族を介護する為に休業している人の代わりの業務(職場復帰するまで)
※その業務が1カ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者(原則として正規の従業員)の1ヵ月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下の業務
業務の種類によって派遣受入期間に上限はありますか?
いわゆる自由化業務(一般的派遣業務)では、派遣先は、就業場所ごとの同一の業務に、派遣受入の制限期間を越えて派遣労働者を受け入れてはなりません。
抵触日とは?
労働者派遣法では、自由化業務について、派遣受入期間に制限を設けています(原則1年で、一定の要件を満たせば最長3年まで延長可能)。
抵触日とは、この期間の制限となる日のことです。
派遣の期間制限は、派遣先の同一の場所、同一の業務について行われるもので、派遣される人材を入れ替えたり、別の派遣元から派遣を受け入れても、
派遣可能期間は更新されることはありません。
抵触日以降は、クーリング期間(派遣労働を受け入れない期間を3カ月と1日以上)を設けるなどの措置をとらなければ、新たに派遣を受け入れることは出来ません。
派遣の適用除外業務(禁止業務)はありますか?
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関連業務
5.労使協議など使用者側の当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など士業の一部
以上が派遣禁止業務とされています。